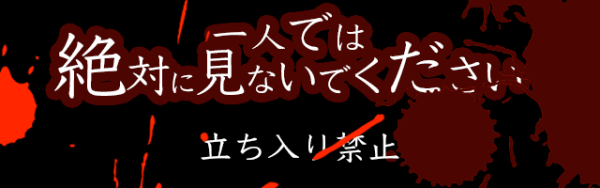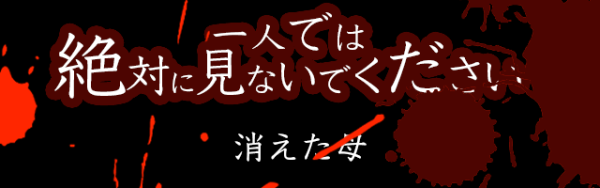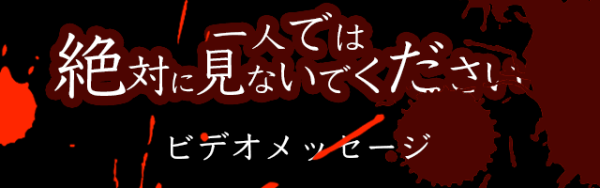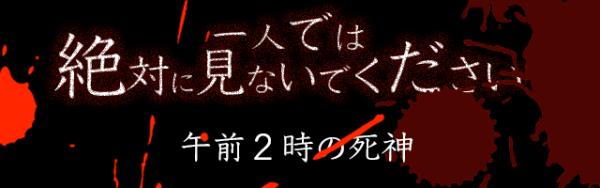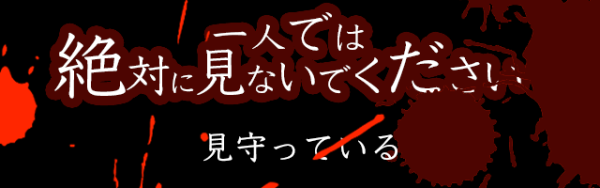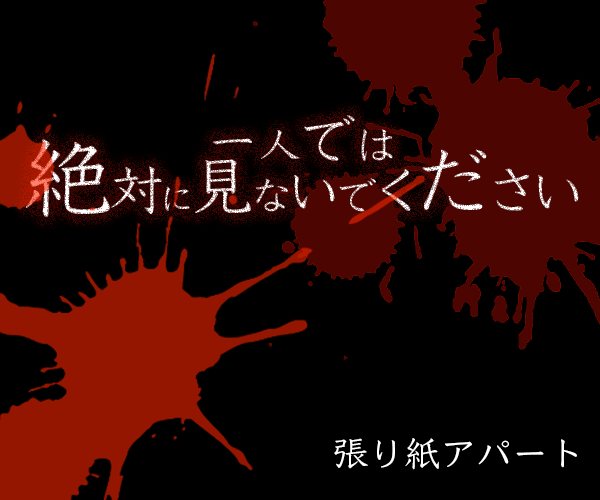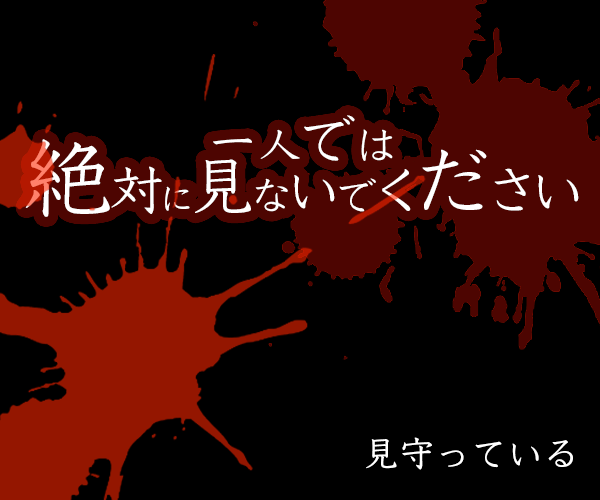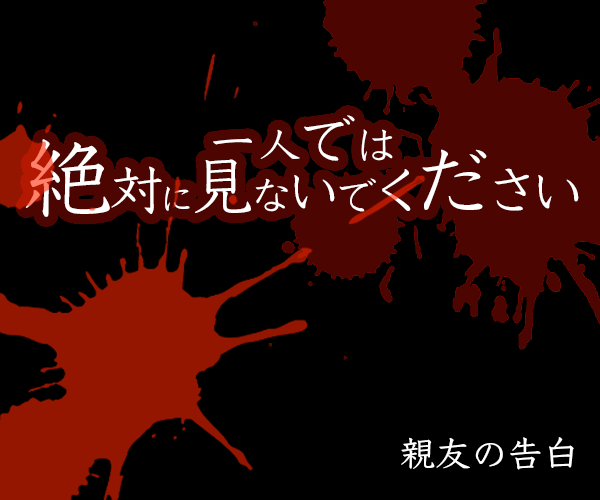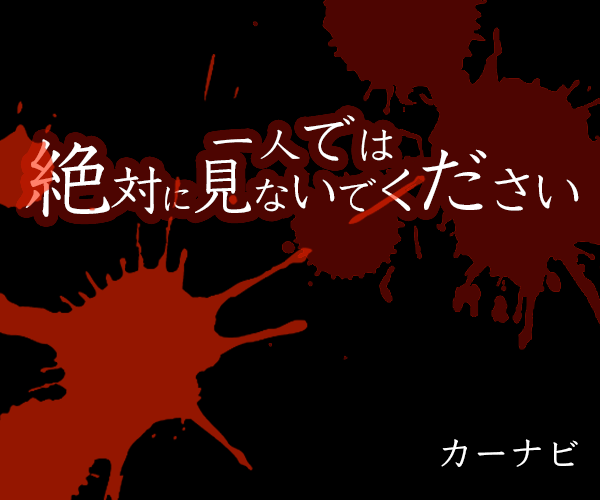見守っている
詩織は、メイドカフェ激戦地区において比較的レベルの高いメイドカフェで働いていた。
明るい性格に容姿が良いことも手伝って、半年ほどで詩織は人気ナンバーワンのメイドになった。
ただ、最近気がかりなことがある。
それは先月ごろから店に通い始めた「ぴくしー」という名前の客のことだった。
「今日も来るかなあ、ぴくしーさん」
「やだなあ…」
憂鬱な顔をする詩織をからかうように、先輩メイドの美月がぴくしーの真似をして眼鏡を上げるふりをする。
ぴくしーはいつもヒビの入った眼鏡をかけていて、汗でずり落ちる度に素早く上げるのだ。
彼は店に来たその日から詩織のファンになり、詩織のブログにも一日に何度も書き込みをしている。
そして、毎日仕事の昼休みを利用して店にやって来るのだ。
プロの人形師であるということ以外には何をしているのか不明だが、常に手製の「しおりちゃん人形」をテーブルに置いている。
「お帰りなさいませ! ご主人さま」
「おかえりなさいませ~!」
今日はもう一人、リリーというメイドが来るはずだったが、来られなくなったため二人で切り盛りしなければならない。
出来ればあまり混まないでほしいと願う二人の思いとは裏腹に、開店と同時に「ご主人様」たちの席取り合戦が始まった。
この店ではランチタイムに限り、三回のミニステージがあるため、ステージにより近い席に座れなければ敗者なのである。
「ご主人さま! ちゃんと並んでくださ~いっ!」
「お前ら! しおりたんが並べって言ってるんだから、ちゃんと並べ!」
「ルールは守れよ!」
ルールをきっちり守る派と一部の過激派で、開店時は大抵こうなってしまう。
美月はそんな状態を内心では面白がっているので、あまり真剣に注意せず誘導等は詩織に任せている。
ようやく落ち着いたところで、一回目のステージが始まろうとしていた。
そのとき、いつもより早くぴくしーがやって来たのだ。
「お帰りなさいませ! ご主人さまっ」
詩織はぴくしーを一番後ろの席に案内した。
そこしか空いていなかったのだ。
「しおりちゃん、今日も…その…、かわいいね…」
「ありがとうございますっ」
そのやり取りに、他のテーブルからの陰湿な冷笑が響く。
ぴくしーはバツが悪そうに眼鏡をくいっと上げた。
「楽しんでいってくださいね…、ぴくしーさん」
「…し、しおりちゃん…!」
この店において、客が「ご主人さま」ではなく名前で呼ばれるのは非常に名誉なことなのである。
ぴくしーはもう泣いてしまいそうになっている。
どのグループにも属さないぴくしーは、イベントの際にも肩身が狭そうで、先ほどのような冷笑も今に始まったことではないのだ。
そんな彼のことを、詩織は口でこそ「うざい」とこぼしながらも、内心は気にかけていた。
ブログでも、あえて彼に対してだけ一番にコメントを返したり、日記の中に彼の名前を登場させたりと、詩織なりの優遇をしていたのだ。
そういった詩織の態度が、逆にぴくしーの立場を危ういものにしているということに彼女自身は少しも気付いていなかった。
「ねえ、詩織…。ぴくしーさんのことなんだけど、ちょっと特別扱いし過ぎじゃない?」
閉店後、美月は心配そうな口調でそう言った。
「ええ~? 私、特別扱いなんてしてるつもり…ないんだけどなぁ…」
「詩織は天然だから気付かないだけかもしれないけど、詩織のファンって結構過激派が多いじゃん?まさか詩織に何かしてくるとは思わないけどさ…、ぴくしーさんが危ないんじゃないかなって」
「そんな…」
思いも寄らない忠告を受けてしまった。
美月の言うとおり、もう少し気を付けた方がいいのだろうか。
詩織はアパートに帰ると、シャワーを浴びながらぴくしーについて色々と思いを巡らせていた。
そのとき、ドンドンドンドン! と、ドアを叩く音が響いて我に返った。
バスルームは玄関の隣なので、まるでバスルームのドアを叩かれているような錯覚に陥り、詩織は小さく悲鳴を上げてしまった。
「びっくりした…。誰だろ…こんな時間に…すごい勢いで……」
身体にバスタオルを巻いてドアの覗き窓から外の様子をうかがうと、そこには見覚えのある顔があった。